どうもうっつーです!
さて今月発売のバンドジャーナル10月号に吹奏楽団の作り方の記事が掲載されたのでと「吹奏楽団を作りたいけど作り方がわかんないよ〜」という人の為に色々記事を書いてきました。
今回は立ち上げる前に知っておくべきことの記事をまとめて、それを踏まえた上で私うっつー先生が今吹奏楽団を立ち上げるなら・・・という立ち上げ方の提案をしたいと思います!
それではまとめ!行ってみよう!!
うっつー先生の吹奏楽団の作り方
①吹奏楽団を立ち上げる前に知っておきたいこと〜はじめに〜
1つ目に記事では「はじめに」と題して
吹奏楽団を作ることは簡単だけど、継続して運営するのは難しいよ
ということを書きました。
人を集めて練習をして、本番をするという流れは至ってシンプルですし意外と人も集まるので立ち上げた時は簡単だけれども、組織運営の問題や人間関係の問題でうまくいかない事だらけです。
楽団を作るということは会社運営やお店運営とほぼ同じで、組織の問題やイレギュラーを解決する能力が必要になってきます。問題処理能力ってやつですね。また人を動かすだけの人望だって必要だし、人の見えないところで泥水を啜ることだってあります。大変です。
それを踏まえて絶え間なく情熱を捧げられる人じゃないと痛い目しかみないのでよく考えましょうね!って記事を書きました。
②吹奏楽団を立ち上げる前にコンセプト・方向性を決めろ!
2つ目の記事ですが
まず吹奏楽団を立ち上げる前にどんな楽団なのか方向性を決めましょう
ということを書いてます。まず最初に決めるべきことだと強く思っています。
これは私の最初の失敗談ですが、方向性を決めなくても最初は楽しかったのですが、結論としては方向性の違いで不満が出たり、自分の思うように行かずに続きませんでした。ここで学んだのは
趣味だからこそ本気でやりたい人と趣味だから気を抜いて遊びたい人を混ぜると危険ということ
楽団の方向性を決めないと同じ感覚を持った人が集まらないので結果不満も溜まりやすく人間関係の悪化が顕著です。学生時代の吹奏楽部の文化ってそれぞれですし、考え方は人それぞれです。相反する考えを持った人が集まると人間関係が悪化するのは目に見えているので、楽団を前に進めやすくする為にも楽団の方向性とコンセプトは決めておきましょう。
この記事では私の吹奏楽団をモデルにコンセプトと方向性を決めて入団条件の例も書いています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:うっつー先生の吹奏楽団の作り方〜立ち上げる前にコンセプトと方向性を決めろ!〜
③吹奏楽団にはこんな係が必要
3つ目の記事は
吹奏楽団にはこんな係が必要で独裁的な運営がおすすめ
ということを書いています。
普段の運営を回す人、演奏会運営ができる人そしてそれをまとめる団長で基本OK
そしてできるだけ2.3人で運営をした方が「意思決定」は早いので後手後手にならずにスムーズに運営できるかなと。後手後手になると団内の雰囲気が悪くなりますしモチベも下がりますからね。
ってことを書きました。係の仕事も多く大変です。
関連記事:うっつー先生の吹奏楽団の作り方〜係の仕事について〜
④吹奏楽団の普段の運営でかかるお金
4つ目の記事では
吹奏楽団の普段の運営には場所代・楽譜代・打楽器代がかかるよ
ということを書いています。
場所は非常に抽選や空室争いがすごくて常に見張っていくことが重要ですし、特に打楽器に関しては吹奏楽団の永遠の課題と言っても過言じゃないくらいには大変です。
また私うっつーも初期費用に250万打楽器と運搬車にかけた経緯も話しています。
関連記事:うっつー先生の吹奏楽団の作り方〜普段の運営でかかる費用について〜
⑤吹奏楽団の演奏会でかかる費用について
5つ目の記事では
演奏会にかかるお金はピンキリだけど大体こんくらいやで
ってのを記事にしています。
会場費に加えて打楽器のレンタル費やパンフチケット代、スタッフへの謝礼色々あるよ〜ってのを説明した上で予算が50万円クラスならこの規模感。100万円クラスならこの規模感っていうのを書いてます。
まとめにくかったのですが実体験をもとに書いているのでイメージがつきやすい形でおさまったかなと思います。
関連記事:うっつー先生の吹奏楽団の作り方〜演奏会にかかる費用について
立ち上げ方の提案
- 吹奏楽団立ち上げるのは簡単やけど継続は大変だぞ
- 立ち上げるならコンセプト先に決めた方がいいぞ
- 係の仕事はこれだけあるから独裁的な運営のがいいぞ
- 普段の楽団運営ではこれだけお金がかかるし打楽器問題は永遠の課題だぞ
- 演奏会開くにはこれくらいお金が必要だぞ
って順番で記事を色々書いてきましたがいよいよ立ち上げ方の提案です。
何度も言いますがたくさん失敗してきた私うっつーがおすすめする吹奏楽団の立ち上げ方はこんな感じの順序で次は立ち上げると思います。
- 楽団のコンセプトと方向性を発起人1人で決める
- コンセプトが決まったら入団条件を決め楽団の規約も作る
- 方向性が決まったらそれに賛同してくれる仲間2.3人口説く
- 賛同してくれる仲間を中心に仕事の配分を決める
- ネットで広く募集する前に知り合いから誘っていく
- ネットで広く人を募集する
- 体験練習会を2.3度開く
- 最終的に活動してくれる人を本入団とし活動を始める
楽団のコンセプトや方向性は発起人が最終的に長く活動すると思います。団が長く続く中で発起人の人が「こんなバンドを作りたいわけではなかった」と思うようなバンドの変遷が起こるくらいなら最も重要な根幹の部分は自分で決めましょう。
その次に幹部集めです。ここは最初に共感してくれた仲間を口説くのが得策かなと思います。できるだけ初めましての人は避けて長く付き合いのある人を口説きましょう。いない場合は一人で全部やる覚悟を持ってください。色々やっていく中で楽団に対して熱い気持ちを持ってくれる人もいますのでその中で信頼できる人に任せていくことが無難です。
ともあれ発起人たるもの、良い意味で最大の人たらしになることが重要です。
そして色々決まったらまずは身内から集めましょう。身内を固める最大のメリットは同じ価値観で吹奏楽をしてきているので基本的な考え方や吹奏楽の文化による違いでの揉め事は起きません。また身内の方が裏切りません。仲悪くなったり面倒ごとは今後の人間関係や周りに影響するのでみんなに迷惑をかけないように楽団で過ごす方が多いと思います。
最後に広くネット上で集めてみましょう。ここで言い方が悪いんですけど「吹奏楽団を立ち上げるので興味ある人連絡ください」というと言葉通り色んな人が集まってきます。いい人ばかりではありません。私が立ち上げた時にも出会い厨みたいな人もいましたし、いざとなったら音信不通になって迷惑をかける人もたくさんいました。
大部分はいい人が多いんですけど・・・みたいな善人ぶったことは言いません。
考え方を変えて方向転換した際には「選民思想だ!お前が一番偉くはないんだぞ!」と言われたこともありましたがこれで正解だと思います。いろんなゴタゴタが団員間でもあったからこそ、最初は2.3回練習機会を設けて実際に合奏をしてみて、最終的に楽団に入るかどうかの意志確認はその後に入団条件等含めて説明して正式入団みたいにして立ち上げるといいと思います。
もう一度言います。ここキチンとやらないと人間で苦労します。
まとめ
今回までに色々と吹奏楽団の楽団運営について書いてきました。
立ち上げ編としては一応これで言いたいことは全てなので一区切りなのかなと思っています。
※また色々立ち上げのことで書きたくなったら追記します
吹奏楽団の立ち上げとは個人的に「恋愛」に似ていると思っていて最初はものすごく楽しいです。いろんな人がニコニコ楽しく協力してくれたり、なんだかワクワクするので夢や希望に満ち溢れる感じがします。
しかしながら半年、1年と続けていくとだんだん色んな人のワガママな部分や嫌な部分も見えたり、人間関係の問題は出てきますしモチベーションが下がってくるものです。
その時に離れる人は離れますし、恩を仇で返すような薄情な辞め方をする人も出てくるので人間不信になる時期が絶対来ると思います。
しかしながら最初に立ち上げた時の情熱を忘れずに「もうそういうもんだ」と割り切れるメンタルを早くに持ち、色んな人間の問題が起きた時には処理できるように対策をしておくのが立ち上げる人は大切になってくる精神なのかなと思います。
吹奏楽は楽しいものです。しかしながら運営と人間関係はまた別で基本しんどいものです。
演奏したいだけならぶっちゃけ近くの吹奏楽団に入団したりオフ会や企画バンドに参加した方がめちゃくちゃ楽なのでそちらをお勧めします。
自分のやりたい曲がある。自分で立ち上げた楽団で色んな人の居場所を作りたい。自分の吹奏楽団を作る大義名分がある。などの強い意志がある人は是非挑戦して見てください。
ちょっとネガティブな結びにはなりましたが、楽団運営したことある人なら多くの人が頷いてくれるリアルな内容かなと思います。
この私の経験の記事がどこかの誰かの吹奏楽団の立ち上げに少しでも参考になってくれたら幸いです!それではまたお会いしましょう!!
うっつー先生が運営する吹奏楽団のホームページ
【団員募集しています!】
現在大阪名古屋横浜の3つの吹奏楽団を運営してます!
一緒に吹奏楽をやりたい方はぜひ各団体のホームページからお問い合わせください♪
ホームページ制作の仕方も後々記事にしていきますね!
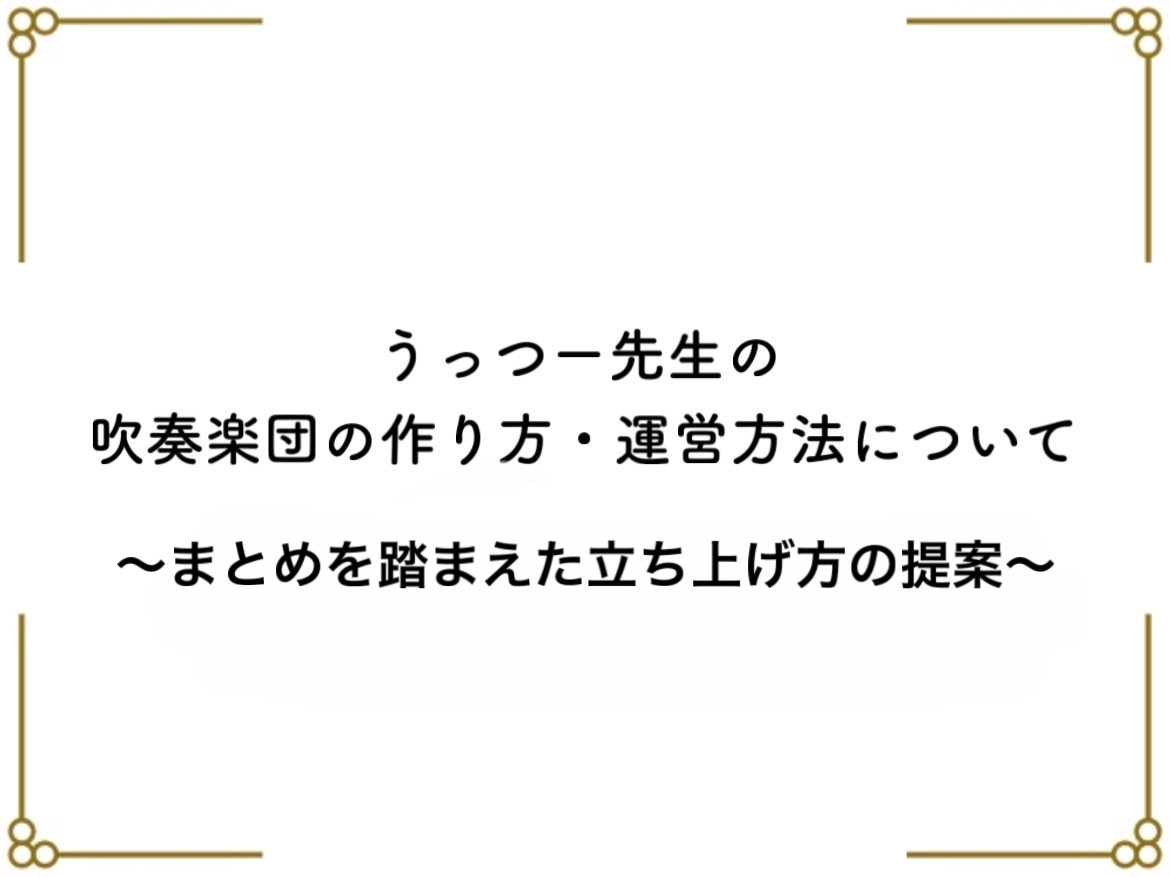
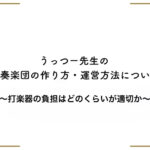
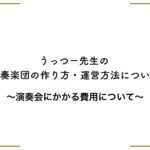
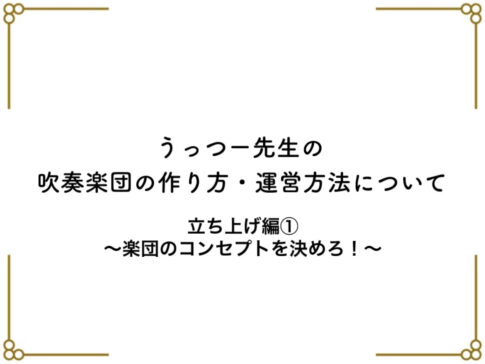
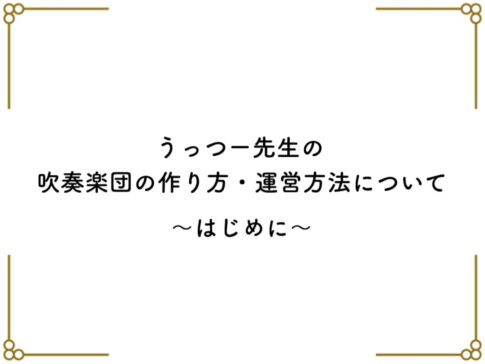
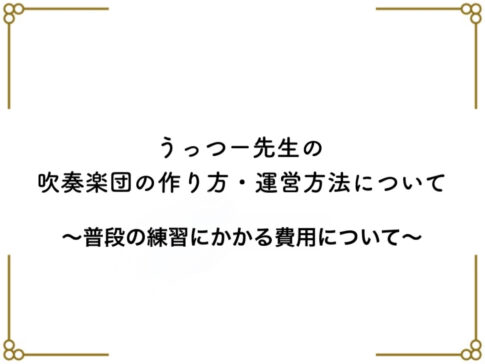
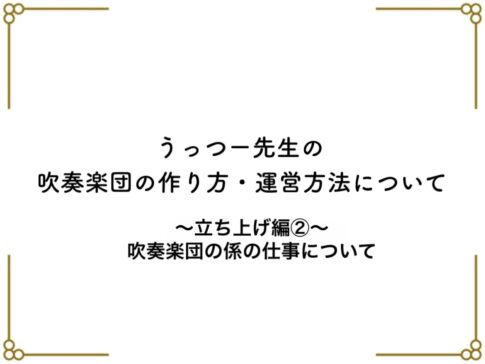
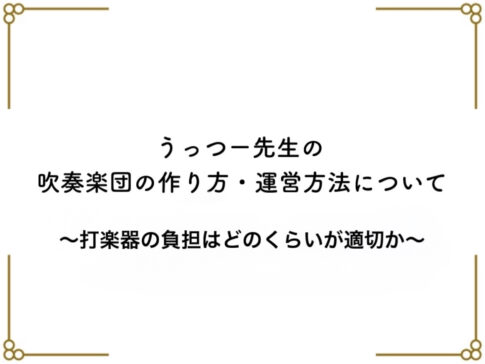
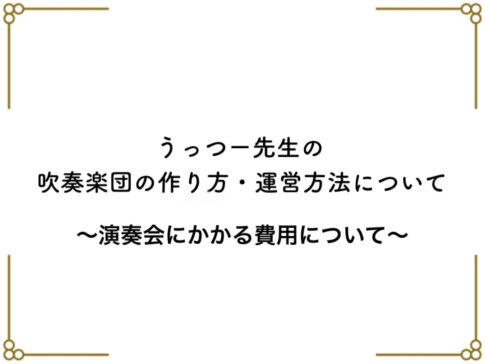


コメントを残す