どうもうっつーです!
前回の記事では「吹奏楽団を立ち上げる前に楽団の方向性とコンセプトを決めよう!」て書きました。
前回の記事:うっつー先生の吹奏楽団の作り方・運営方法〜立ち上げ編①〜楽団のコンセプトを決めろ!〜
今回の記事では
- 吹奏楽団の運営にはどんな係が必要か?
- 吹奏楽団の運営は独裁か権力分散がいいか
をテーマに色々と書いてみたいなと思います!それでは行ってみよう!
吹奏楽団の運営に必要な係
まず大前提ですが運営は色んなやり方があるので下記の係と説明だけが絶対正しいというわけではありません。メンバーのやる気や仕事を処理できる能力にはそれぞれの人や楽団によりますし、地域がらのこともありますので「ふーん」程度に参考にしていただけますと幸いです。
吹奏楽団の幹部について
- 団長(1名)・・・全てのの管理責任を負う
- 副団長(2名)・・・普段の練習管理(1)・本番の管理(1)
- コンサートマスター(1名)・・・団内の練習計画・合奏を担当する
副団長は団長補佐というより、普段の練習運営を取りまとめるリーダー(マネージャー)と本番の運営を取りまとめるリーダー(インスペクター)のつもりで動ける人が好ましいです。
逆に団長はこれらを全てやる勢いの人じゃないと向いてません。これを何年も変わらずやり遂げる確固たる意志がないと楽団は崩れます。長く続ける意志がない期間限定等の楽団やオフ会バンドでも変わらず熱いパッションは必要です。
コンサートマスターは仕事量的には少なそうに見えて、団の演奏レベルに直結するので指揮者の先生以上に勉強はもちろん、不足しているパートがある場合代奏の指示や、出席がまばらの中でのバランス指示など、指揮者の先生がいてもいなくても毎回出席して管理する必要があるので重要です。
普段の練習運営に必要な係
- 渉外・・・練習の場所取り・ホールの抽選などを担当する
- 運搬・・・打楽器などの運搬を担当する
- 楽譜・・・必要な楽譜を準備・著作権まわりを担当する
- 記録・・・練習の記録や録音を担当する
- 広報・・・SNS更新やホームページ更新を担当する
- 人事・・・見学者のメールの対応と当日の対応を担当する
- 会計・・・団に関わるすべての会計を担当する。※3人以上推奨
これらが普段の練習運営に必要になってくる係なのかなと思ってます。
主にこれらを会計以外は副団長(マネージャー)が一人でやるのが理想的です。できないのであれば信頼できる団員と分担してやりましょう。特に渉外と運搬は副団長は目を光らせておくといいです。普段の練習が滞りそうになるのはここが主なので。
また色々細分していますが例えば「記録と広報、人事」は連動性や相性がいいので一緒にしてみてもいいかもしれません。それは各団体作るときにやりやすいように決めていただいて構いません。
また会計は係の仕事に入れていますが、幹部からは独立していた方が絶対いいです。勝手に色々と団のお金を自由に使えるようにすると私物化や横領の引き金にもなりますので団員から3人ほど立てて管理監査をするようにすると変なツッコミや揉め事が起きないかなと思いますね。
本番を行う際に必要な係(定期演奏会などの例)
- セッティング・・・演奏会のセッティング図制作・ひな壇の組み上げなど
- タイムスケジュール・・・本番の日のスケジュール作成
- 司会・・・司会者用の原稿を作成
- 照明・音響・・・本番の照明と音響を担当する(ホール側がやることが多い)
- ステージマネジメント・・・照明のキュー出しやスケジュールの管理
- 打ち合わせ・・・本番会場と演奏会の打ち合わせなどを担当
- デザイン・・・フライヤー・チケット・パンフなどのデザインを担当
- 集客・・・チケットの管理、集客がどれくらい集まっているかを担当
- スタッフ依頼・・・演奏会の受付・ドアマンなどの人探しや依頼を担当
これも色々細分して説明していますが正直あまり細分して人に任せるより責任を持って遂行できる人に独裁的に任せた方が良いです。理想は副団長(インスペクター)の一人がやると良いでしょう。団長に一任してもいいです。演奏会実行委員長を作って一任してもいいです。なんでもいいですとにかくできる人に任せてください。(メチャクチャ重要)みなさん仕事や学業の合間に係の返事を返すので、意思決定が遅れたり情報錯綜すると後手後手になります。
私たちの楽団では私、うっつーが演奏会で大切なタイムスケジュール作成・照明音響・ホール打ち合わせ・スタッフ依頼をおこなってます。セッティング表や司会原稿、デザイン、集客は人に任せても大きく遅れを取ることは基本ありませんが、ホール側と連携するものに関しては強いリーダーがいた方がいいです。(その分大変なんですけど汗)
吹奏楽団の運営の意思決定は独裁的が良いか権力分散が良いか
吹奏楽団の運営は独裁的な方が圧倒的に良い
吹奏楽団の運営ですが、結論おすすめは独裁的な運営です。
注目すべきは意思決定の速さなのかなと
独裁的な運営と聞くと聞こえが悪いですし、権力を分散してみんなで仲良く物事を決めるというのは非常に聞こえがいいのですが、残念ながら社会人バンドは学校の部活とは違いみなさん毎日会うわけでもなければライフサイクルが違いますので会議の時間の調整も難しいです。また賛成と反対が分かれてしまうと楽団としての意思決定までに時間がかかります。
意思決定までに時間がかかるとやらなければならない仕事が滞り後手後手になります。後手後手になると当たり前ですが楽団の士気も下がり楽団は停滞します。
またこれはたくさん失敗したり嫌な経験をしてきたので「そういう風に考えてしまう自分嫌だな」と思う話なんですが、最初は「一緒に熱意を持って楽団を運営したい!」と言っている人でも1.2年経つだけでモチベが下がる人もいます。仕事や学業、家庭の環境も変わる人がいます。言い方は悪いんですけどどんなに最初に燃え上がってやる気あるな〜と思う人でも所詮そんなもんです。残念ながらこの12年の楽団運営してきてそういう人にたくさん出会ってきて失敗した結果、基本一人で運営やれた方が楽だなぁと思いました。(たくさん協力してくれた人ももちろんいますが)
ですのでスピード感持って楽に動けるのは独裁的な運営の方です。
権力分散のメリットは仕事と責任の細分化くらいかなと思ってます。スピーディに仕事が回るなら、みんなが仲良くできるならやった方がいいに決まってます、が権力の分散はデメリットの方が吹奏楽団の運営は多い気がします。(もう一度言いますがみんな毎日会わないし、ライフスタイルも違うし、熱意もだんだん下がります)
しかしながら全てが独裁的だったり、団員側の意見が通りづらいと当たり前ですが不満は溜まっていきます。ここのいい塩梅を目指しながら作るといいのかなと思いますね。
おすすめしたい独裁的な運営について
自分で書いててすげえタイトルだなあと思うのですが、おすすめしたい独裁的な運営方法についてです。
- 最終的な意思決定は団長が決める
- 会計は権力を分散しておき、独立させておく
最終的な意思決定は団長が責任を持って決めるといいかなと。
しかしながら団員の意見も反映しないといけないのでGoogleフォームなどでアンケートをとります(選曲やどんな演奏会にしたいか。楽団の方向性など)もちろん票や希望の多いものを選ぶといいのですが、理想と現実やよく見極めて取捨選択はしなければ激オモプログラムばかりだと演奏会は失敗するし、楽団の方向性もその都度右にいったり左にいったりするとブレて抜けていく団員や入ってくる団員の質にも関わってきます。
ですので団員が何を思っているか、求めているのかと楽団の根幹の部分を照らし合わせて意思決定していくことが重要なのかなと思いますね。団員はお客様じゃありませんので意見のアベレージを取ることも大切ですが時にはグイッと舵を切るのも大切です。それが運営の強い楽団づくりをするために必要な団長の権限なのかなと。
会計は独立させておくは上記の通り。再度書きますが、幹部からは独立していた方が絶対いいです。独裁的になると勝手に色々と団のお金を自由に使えるようにすると私物化や横領の引き金にもなりますので団員から3人ほど立てて管理監査をするようにすると変なツッコミや揉め事が起きないかなと思います。
まとめ
今回の記事では「係の仕事はこれだけありますよ〜」と明示しつつ
「できるならこの係の仕事は多くの人と分担するより2.3人で回せるといいよ〜」
ってことを書きました。
私は大阪名古屋横浜の3つの吹奏楽団の運営をほぼ1人で行なっています。これができるのはスピーディーに意思決定ができるからだと思います。誰かと話し合い、許可を取り、責任を分散するだけ面倒なことは多く何事も後手後手になります。
独裁的な楽団運営は責任が重い分、批判ももちろんあるしうまくいかなければ風当たりはかなり強いです。団員がごっそりやめるなんてこともありますが、良い意味で人はその分淘汰されます。理解ある人が残ってくれるので、私みたいに強い覚悟を持ってやりたい人がいるのであれば独裁的にやってみる方がおすすめです。
色々書きましたが最終的にこれを読んでいる読者のみなさんが組織を運営したことがあるかで見方がだいぶ変わる記事なのかなと思っています。
楽団運営は大変なこともあるかと思いますがぜひ挑戦してみてください!
わからないことがあればご相談も受け付けてますのでぜひお気軽にご連絡くださいね!
うっつー先生が運営する吹奏楽団のホームページ
【団員募集しています!】
現在大阪名古屋横浜の3つの吹奏楽団を運営してます!
一緒に吹奏楽をやりたい方はぜひ各団体のホームページからお問い合わせください♪
ホームページ制作の仕方も後々記事にしていきますね!
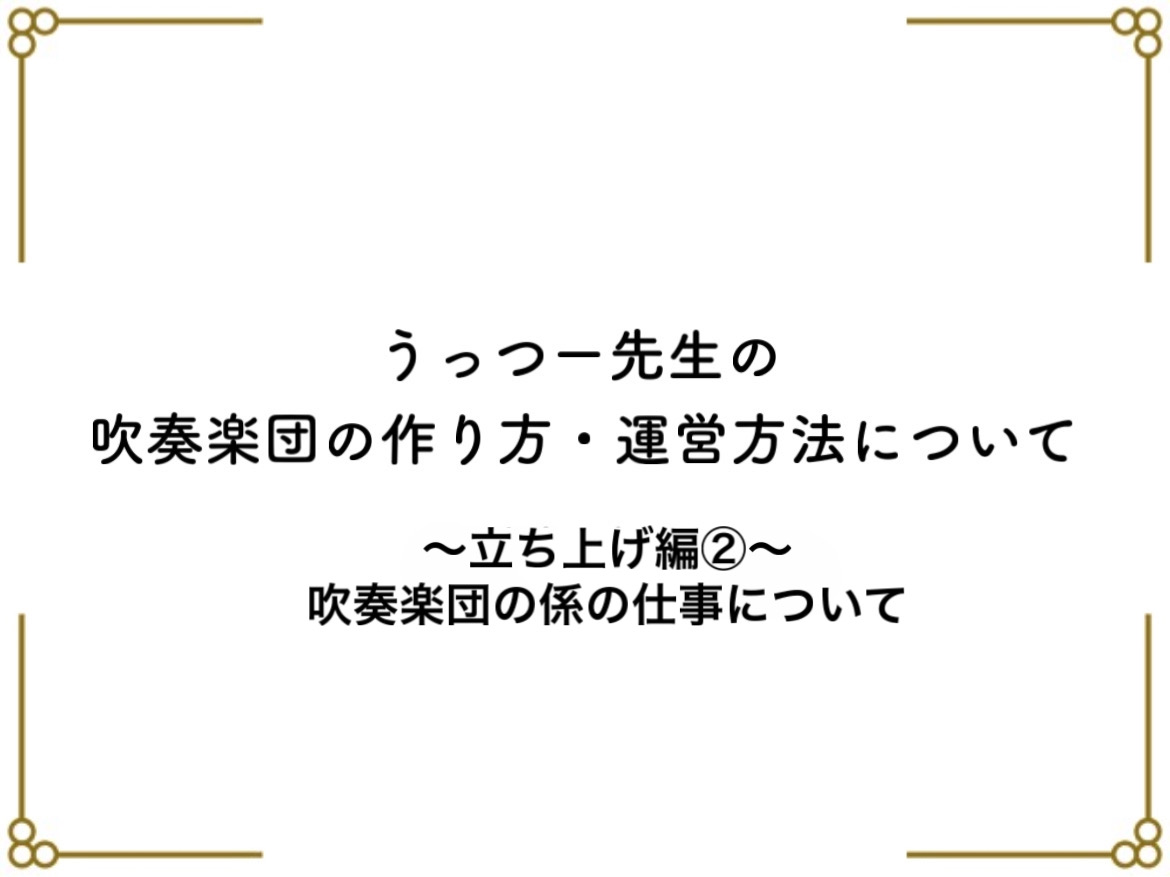
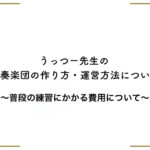
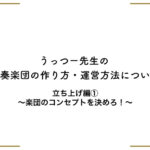
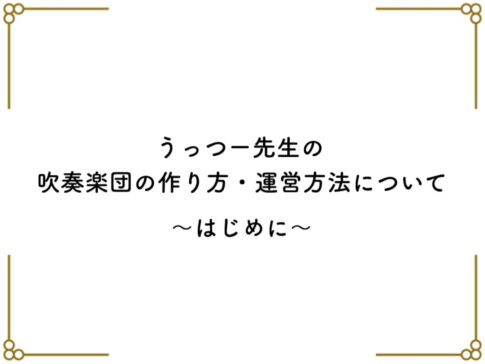
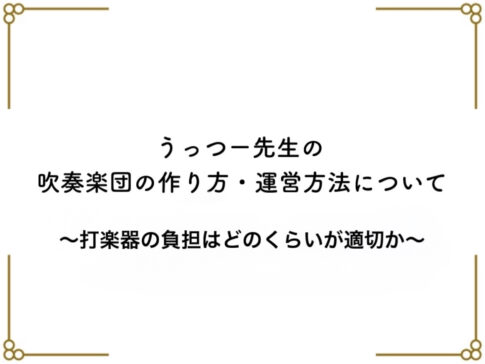
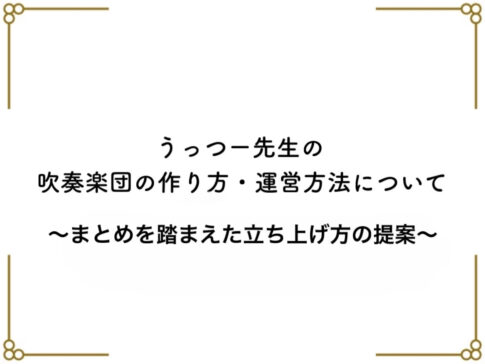
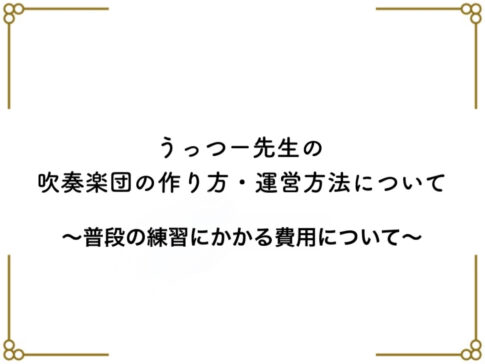
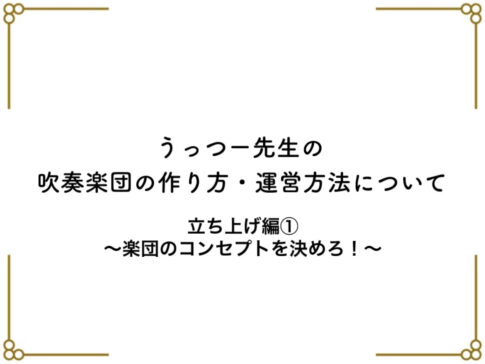
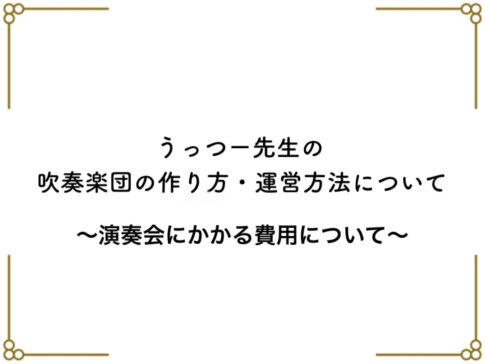


コメントを残す