どうもうっつーです!
前回「吹奏楽団を作るのは意外と簡単だけど、立ち上げた後の運営が大変だよ〜」と書きました。
前回の記事:うっつー先生の吹奏楽団の作り方・運営方法について〜はじめに〜
それでもなおこの記事を見ていると言うことは皆さんやっぱり熱意がある人なんでしょうね
はい。つまらないおふざけはここまでにして
今回の記事は私うっつーがもう一度吹奏楽団を1から作るならこうやって作る!みたいなことを書いていけたらと思ってます。
19歳の頃から楽団を作っては分裂したり潰したり、オフ会をしまくってた自分だからこそ経験した色々な失敗や意外とあるあるな落とし穴などをも踏まえてかけたら。なんとなくどのバンドも立ち上げたら通る失敗ってありますので!
それでは行ってみよう!
楽団を立ち上げる前にやるべきこと
最初に作った吹奏楽団で失敗した時の話
吹奏楽団を立ち上げるときに「とりあえず人を集めたらなんとかなる」みたいな考えは危険です。
今となっては「当たり前だろ〜」って話ですが
当時は右も左も分からなかったんですよね〜
19歳大学1年生当時の自分は「一緒に吹奏楽やろうよ〜」「みんなで楽しくやろうよ〜」なんて行って福岡の地元の友達や先輩後輩を集めて吹奏楽団を立ち上げた経緯があります。
最初の1年はめちゃくちゃ楽しかったのですが、結論としては方向性の違いで不満が出たり、自分の思うように行かずに続きませんでした。仲も悪くなってしまった人も正直います。未だに飲みに行く仲のいい人もいますが(申し訳ないなとも思います。もう10年以上も前の話ですけど)
また後々に立ち上げた吹奏楽団や期間限定の吹奏楽団でも反省をもとに色々コンセプトは決めたはずなんですが、事細かに決めてなかったのでなかなかバンドを運営するのは大変でした。
ここで学んだのは
趣味だからこそ本気でやりたい人と趣味だから気を抜いて遊びたい人を混ぜると危険
ということです。
吹奏楽において作曲者に対してリスペクトを持ちストイックに練習して音楽を作りたい人も入れば、気を楽にしてみんなとワイワイしながら練習後は居酒屋で一杯やりたい人もいます。
どちらが良くてどちらが悪いとは言いませんが、この「楽しい」のベクトルの違うもの同士が混ざると「なんであいつ練習してこないの?」「なんで趣味なのにそんなにカリカリしてるの?」となり人間関係の悪化と楽団の分裂につながります。
吹奏楽団を立ち上げるなら最初に方向性(コンセプト)を決めろ
以上の経験より方向性の違いや楽団への向き合い方の違いで揉めないように
まずは楽団のコンセプトを決めたり、周りの練習できる環境、打楽器や楽譜を買う時の試算を綿密に行ってからスタートする方が人間関係や環境、お金での揉め事は減ります。(書けば当たり前なのですが決め方が甘いとなかなか大変です。)
最近の私の吹奏楽団ではないのですが、曖昧なバンドだと
「そんなの最初に説明がなかった」
「思ってたのと違かった」
と言われて揉めたり、相手との意志の相違で楽団を辞めると言うのが多くなります。
では楽団の方向性、具体的にどのようなことを決めればいいのかについてですが最低限以下の項目の方向性は決めていた方が無難です。
- コンクールに出るのか出ないのか・出る場合はどのレベルを目指すのか
- どんな曲を主にする楽団なのか(誰が選曲するのか割と揉めます)
- どこの地域を中心に練習をするのか
- どの年代が中心なのか
- 入団条件・退団条件はどのようにするべきか
とりあえずざっくりはこの辺なのかなと。
コンクールの項目を例に出しますが、コンクールは最初から出る出ないは決めた方がいいです。
いつか出てみたいとか曖昧にしてしまうと、その時が来たらコンクールに出たくない人はゴッソリ抜けて楽団の基盤もフラついてコンクールに挑戦できなくなることもあります。
またそのいつかが叶わなかった時はコンクール出たい派の人たちはウンザリして別の楽団に行ってしまいます。
またコンクールに出るにしても全国を目指すのか、支部大会を目指すのか、県大会で金賞を目指すのかとりあえず出てみるのかでも集まる人の質は変わってきます。また練習量が決まってきます。
これらをハッキリすることで、大体どんなバンドなのかってのは入ってくる人は予想できますし、入る前に合う合わないを判断するので同じ方向性の人が集まってきますので楽団がブレにくいです。
他の項目についても同じで方向性次第で合う人が集まってきます。
コンセプトを決めるというのは楽団の求めている方向性と入ってくる人の考えの擦り合わせになりますのでなるべく事細かに決めていきたいところです。
Puzzle Symphonic Band(大阪)をモデルに
Puzzle Symphonic Bandのプロフィール
2021年4月に創団。20代30代を中心に
「吹奏楽を通して人生を豊かに」をスローガンに大阪市と尼崎市にて毎週土・日に活動中。
吹奏楽コンクール経歴
2022年大阪府大会銀賞
2023年大阪府大会金賞・代表 関西大会銀賞
2024年大阪府大会金賞
2025年大阪府大会銀賞
では私が運営している大阪の社会人吹奏楽団Puzzle Symphonic Bandをモデルに書いてみます。(以下大阪パズル)プロフィールは上記の通り、動画の通りで個人的にはコンクールの結果もちょっとずつ出てきてるバンドなのかなと自負しています(笑)
ゆるっとしたバンドというよりかは結構向上心あるバンドなのかなと思ってます。
Puzzle Symohonic Bandの方向性(コンセプト)
- 吹奏楽コンクールに出場する(全国大会を目指すが、まずは支部金を目標に)
- 選曲はアンケートをもとに先生が行う
- 大阪市と尼崎市で練習をする
- 20代30代が中心(40代以上は交渉)
- 吹奏楽を通して人生を豊かにできる楽団づくり・演奏を目指す。
吹奏楽コンクールに関してはもちろん気持ちは全国大会ですよ!(笑)高みに向けて努力することこそが面白い!って気持ちでやっています。しかしながらあまりにもかけ離れた目標は団員のモチベーション的に絵空事すぎて下がってしまいます。ですので現実的な目標はもう一度関西大会に出場して金賞を受賞する!ってところに重点をおいて練習に励んでいます。
選曲については特にジャンルは決めてません。その都度Googleフォームなどでアンケートをとりますが、すべての曲を取り上げるわけにはいきません。幹部で決めさせることもありますが、基本的には
- 演奏会までの期間の逆算をしながらできるかどうか
- 今のバンドのレベルに合うか、次の演奏会に繋げられるか
この部分を見ながら責任持って経験をもとに私が選曲しています。
練習場所は大阪市と尼崎市とちょっと変わった練習範囲なのかなと思います。実はずっと大阪市で練習していたのですが、コロナ禍の時に立ち上げたバンドなので大阪の施設が緊急事態宣言の時には定員の1/2か1/4しか使えない時期がありました。そのためお隣の兵庫県は定員Maxまで使えたのでそっちで練習してたら兵庫の子や新快速で京都から来る子も増えたのでその名残として今も大阪市と尼崎市で練習しているんです。大阪市でも淀川区など北の方でやってます。そういう理由ですね。
また年代はなるべく近い方がいいです。以前20代しかいないパートに「私大丈夫だから!」と言って入ってきた40代くらいの方が結局「若い人のノリについていけませんでした」と言って勝手にやめていった経緯もあります。歳上の人は大丈夫でも歳が離れると歳下側はやりにくいです。もちろん私のようにどんな年代の人でも仲良くなれる人は別ですし、50代の方でもう何年もサポートしてくれるおっちゃんもいるので全てがそうとは言い切れませんが、歳が離れるとやりづらいことの方が多い気がします。楽団の平均の年齢の±5くらいがちょうどいいかな〜とは思いますね
最後はスローガンなんですけど「吹奏楽を通して人生を豊かに」ってところに焦点を当てて活動をしますと見学に来た段階で説明しております。意味としては部活と違って趣味でやるわけですのでやはり自分の人生が豊かにならないと意味がないと思ってます。しかしながら多くの人と合わせて作る趣味ですしお客様がいるからこそ成り立つ趣味なのでそこに一定のリスペクトと周りの人の人生も豊かにしないといけないですよね?という考えを理解してくれる人に入ってもらっています。
長くなりましたが方向性・コンセプトに関してはこんな感じでやってます。
方向性・コンセプトが決まると入団条件がきまる
コンセプトが決まると後は入団条件が自ずと決まってきます。
以下Puzzle Symphonic Bandのホームページに掲載している入団条件です
- 高校生以上で楽器を個人で所有している方。(打楽器・特殊楽器を除く)
- 毎週の練習に原則参加してくださる方。(月3以上来れる方)
- 合奏までにしっかりと個人練をしてくださる方。(団では個人パート練の時間はとりません)
- 入団後原則1年以上は在籍できる方。(途中退団の場合は残額の団費を請求する)
- 活動記録として写真や動画をウェブに掲載する事に同意してくださる方。
重要そうなもので行くと②の毎週の練習に原則参加してくださる方という項目。これ入団するとだんだん曖昧になってく人がいるので、月3以上という具体的な数字を出した方が守る人が増えたのでぜひ回数は明記した方がいいかなと。またこの条件で入ってきた人で出席を守れなかったとしても基本スルーで全然いいです。大体の人が出席満たなくて申し訳ないと心の底で思っている人多いですので。仕事や学業が突然その時期忙しいことはあるので暗黙の了解で私も何も言わなかったり、「最近忙しいん?落ち着いたら頑張ってな!」みたいな感じでアルフォート渡したりとかしてフォローしてます。基本的に上記のコンセプトと入団条件で来る子は真面目な子が多いので。(流石に1.2ヶ月こなかったら注意するけど)
③の合奏までに個人練してくるというのは団費は個人練(個人)に使うものではなく合奏(全体)に使うものなので団としては個人やパートの時間は取らないと明記してます。これを認めてしまうと譜読みをしてこない人が増えたり、練習してこない人が増えます。すると真面目に個人練してきた人が「なんや、これならわざわざ平日に譜読みしたりしなくていいやん」と団のレベルが下がったり真面目な人からやめていくバンドになります。もちろんコンクールシーズンや演奏会シーズンで時間が取れる時はパートやセクションはするんですけど、普段の少ない合奏時間で個人練なんてとっていたら前に進みませんからね・・・
④の原則1年以上は在籍できる方というのは結構重要かもしれません。以前4ヶ月で更新みたいな感じで運営してたんですけど、人の抜け入りが激しくて団の係の仕事や基礎合奏やルールをその都度1から教えないといけないので長く在籍してた人が疲弊しちゃったんですよね。そして全然楽団の基盤も安定しない。毎月立ち上げ1年目みたいな。また入ったけどすぐやめちゃうみたいな人もいてトランペット埋まったのにまた募集かけないとみたいなことにもなりました。だから原則1年続けられる人で途中で退団する場合は残りの団費をいただく制度にしました。
これ昔Twitterで書いたらめちゃくちゃ批判されたのですが結果やってよかったと思います。というのも見学の段階で「え、残りの団費払うの?それなら辞める可能性あるし入るのやめておこう」ってなるからです。逆に「途中くじけるかもだけど残りの団費払ってでもこの楽団に入りたい」という人が入団するので団に対して覚悟が決まった真面目に活動したい人が入ります。
これ以外には団費を上げるって方法もあります。値段の安い店と値段の高い店では客層が違うように吹奏楽団でも来る人の質は変わりますよね。しかしながら値段が高いとそもそも見学に来る人も少なくなります。いい人に出会う打率が下がるんですよね。ですので私は最低でも1年は続けるって覚悟のある人を多く取りたいので今のやり方に落ち着きました。みんな辞めるどころか長く続ける人が多くなりましたがやっぱ方向性が同じだからなのかなって思います。
まとめ
今回の「楽団のコンセプトを決めろ!」の記事はこれで最後です。
楽団を楽しく、そして長く続けるためには同じような考えや感覚を持った人を集めることが重要なのかなと思います。
もう一度言いますが
趣味だからこそ本気でやりたい人と趣味だから気を抜いて遊びたい人を混ぜると危険です。
どちらの考えでも私は正解だなと思っていますが「楽しい」の方向が違う同士が集まるとなかなか共存するのは難しいのかなと思ってます。
楽団を立ち上げる前はまずコンセプトを決めること
決まったら入団条件が決まってくるのでどんな人に来てもらいたいかを精査し入団条件を決めることです。
次回も楽団を立ち上げる前にすることの記事を書こうと思いますが
- どんな運営の係が必要か
- 運営は独裁がいいか権力分散がいいか
などの運営に関わる内容を深く記事にできたらなと思ってます!
引き続き駄文ではありましたがお付き合いいただきありがとうございました!
これから吹奏楽団を作りたいって方がいましたら一緒に頑張りましょう^^
何かご相談があればぜひご連絡もください。
うっつー先生が運営する吹奏楽団のホームページ
【団員募集しています!】
現在大阪名古屋横浜の3つの吹奏楽団を運営してます!
一緒に吹奏楽をやりたい方はぜひ各団体のホームページからお問い合わせください♪
ホームページ制作の仕方も後々記事にしていきますね!
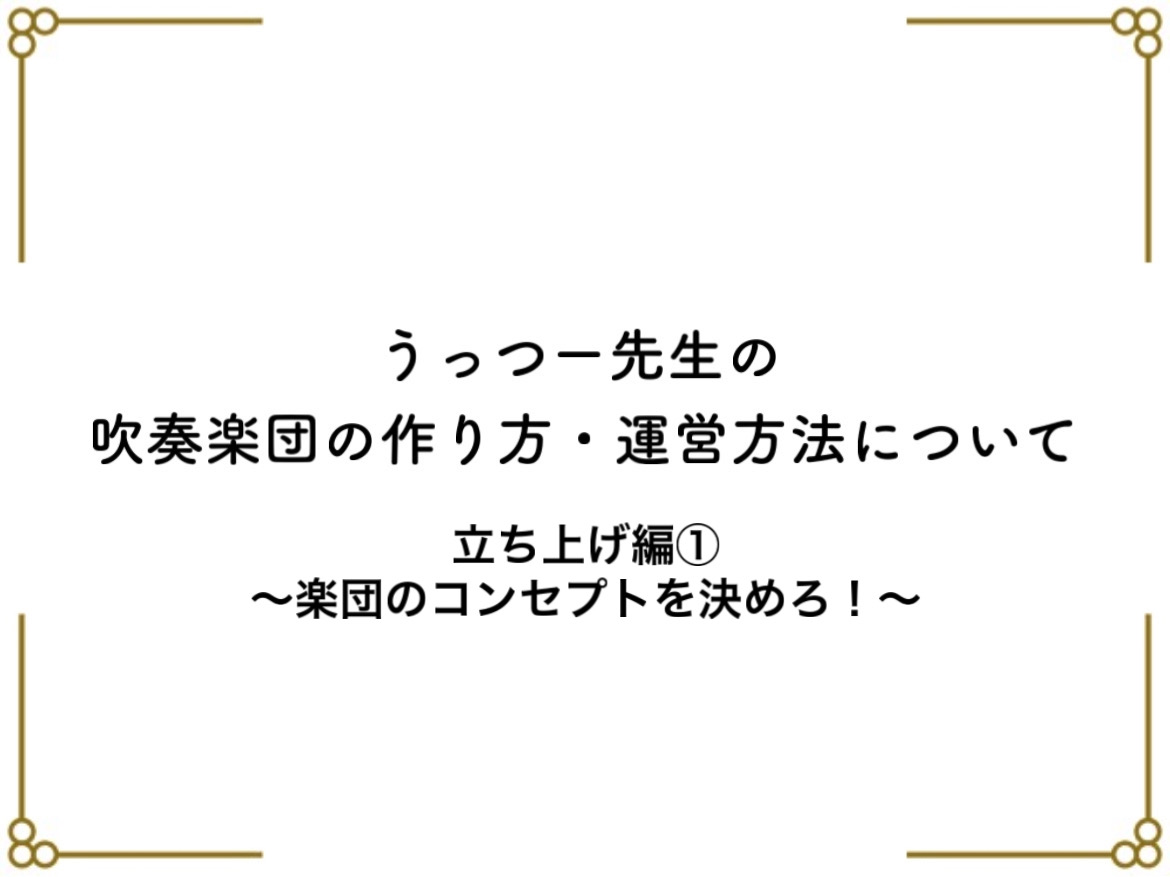
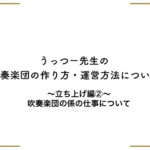
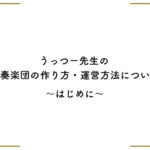
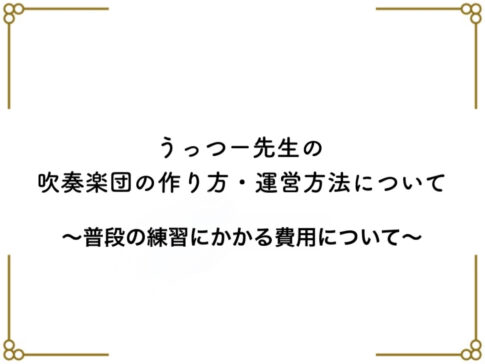
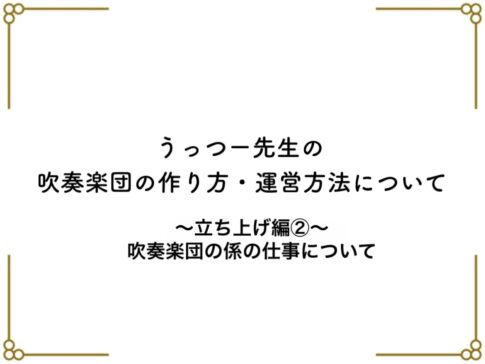
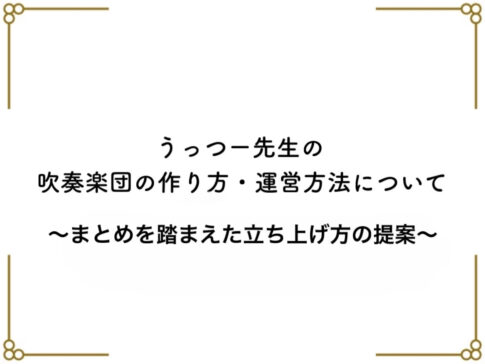
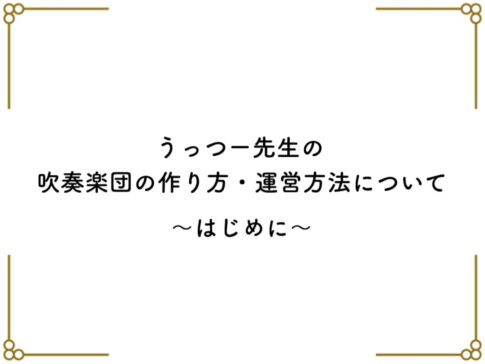
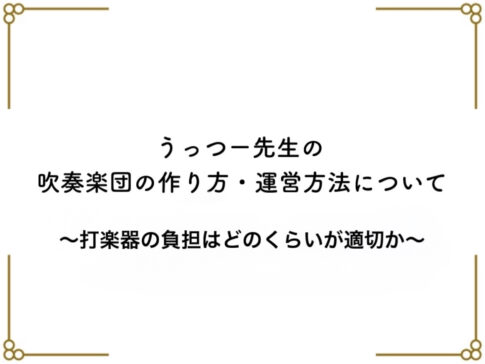
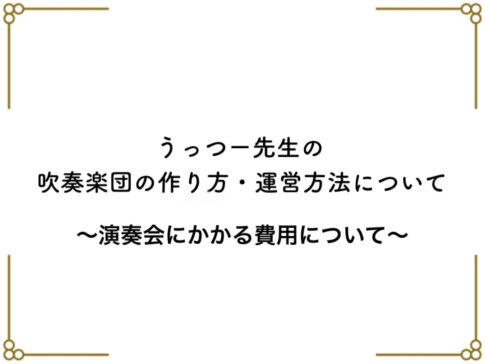


なんて素晴らしい人なんだ!!